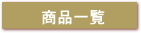2013年07月31日
さば水煮缶のお味噌汁
5~6年前、
大学生活のためにひとり暮らしを始めた娘に教えてもらった、レシピ。
レシピというほどのものでもないけれど、
簡単でいて美味しいので時々作っている、お味噌汁です^^

鍋に、具なしのみそ汁を作ります。
今日は、カツオと昆布だしで、4人分、約800ccです。

サバの水煮缶

200g入りのものです。
汁ごと鍋にあけて

中火に掛けたら

お玉で、かたまりを崩します。
煮立てないように火に掛けて温めたら、出来上がりです。
薬味は、
ネギ・青じそ・みょうがの子

そして、絶対に忘れたくないのが

おろししょうが。
冬は温かく、夏は暑気払いになりますし、
何よりも、美味しい!!
たっぷりと薬味をのせて

いただきます。
シンプルでいてボリュームとコクがあるので
おかずになる一品です。
今回は、サバの水煮缶だけを使いましたが、
カボチャやニンジン・大根など
お好みの野菜たっぷりのお味噌汁にも合いますよ。
是非お試し下さい。
大学生活のためにひとり暮らしを始めた娘に教えてもらった、レシピ。
レシピというほどのものでもないけれど、
簡単でいて美味しいので時々作っている、お味噌汁です^^

鍋に、具なしのみそ汁を作ります。
今日は、カツオと昆布だしで、4人分、約800ccです。

サバの水煮缶

200g入りのものです。
汁ごと鍋にあけて

中火に掛けたら

お玉で、かたまりを崩します。
煮立てないように火に掛けて温めたら、出来上がりです。
薬味は、
ネギ・青じそ・みょうがの子

そして、絶対に忘れたくないのが

おろししょうが。
冬は温かく、夏は暑気払いになりますし、
何よりも、美味しい!!
たっぷりと薬味をのせて

いただきます。
シンプルでいてボリュームとコクがあるので
おかずになる一品です。
今回は、サバの水煮缶だけを使いましたが、
カボチャやニンジン・大根など
お好みの野菜たっぷりのお味噌汁にも合いますよ。
是非お試し下さい。
2010年10月22日
松茸のお吸い物
松茸と言えば、松茸ごはんに土瓶蒸し。
でも、土瓶蒸しにするような土瓶を持っていないので
鍋でできるお吸い物です^^

今日は、松茸の風味をより活かせるように
まぐろの血合い抜き削りを使います。
と~っても上品で自分を主張しないダシなので、
素材の持ち味を存分に引き出してくれます。

”血合い”は、魚の赤黒い身の部分のこと。
”血”というくらいですから、ミネラルや鉄分などの栄養価も高く、
ダシを取ったときには、この血合い部分がコクを出してくれます。
ですが、濁りの原因ともなるので、
澄んだダシを引きたいときには、血合いを取り除いたものを使います。
もちろん、ご家庭でのお料理には血合い入りで充分ですし、
お好みのおだしでO.K.ですよ~^^
鍋に
水 1リットル
昆布 10g
を入れて中火に掛けます。

湯気が立ってきたら、プツプツ沸騰してくるまえに
早めに昆布を取り出します。

取り出した昆布は、2番だしが取れますよ。
沸騰したら
コップ1杯くらいの差し水をして、

削り25~30g を入れます。

ひと煮立ちしたら火を止め、

そのまま1~2分置きます。
削りが沈むまで待つのが理想のようですが、
なかなか沈まないので、1~2分置いたらこします。

ここに、
日本酒 大さじ 1/2

塩 小さじ 1/2

を入れて、味加減をみます。
1リットルよりもやや多目のダシの量ですから
と~っても薄味ですが、
この控えめな味がいいんですよ~^^
松茸 1本
乾いた布巾で汚れを拭き取ったら

石づきを落として

食べやすい大きさに切って
鍋に入れて、

沸騰させないように2分くらい中火に掛けます。

一つまみの塩を入れてゆでて

薄皮をむいた、銀杏。

輪ゴムでまとめて、

ひとつまみの塩を入れたお湯でさっとゆでた
三つ葉を

お椀に入れておいて、

注ぎます。

ちょっと薄かったかしら~ と感じるひとくち目ですが、
二度目に口に運んだとき、
美味しい~!と、感動できます。
ダシの奥深さを堪能できる一品です^^
でも、土瓶蒸しにするような土瓶を持っていないので
鍋でできるお吸い物です^^

今日は、松茸の風味をより活かせるように
まぐろの血合い抜き削りを使います。
と~っても上品で自分を主張しないダシなので、
素材の持ち味を存分に引き出してくれます。

”血合い”は、魚の赤黒い身の部分のこと。
”血”というくらいですから、ミネラルや鉄分などの栄養価も高く、
ダシを取ったときには、この血合い部分がコクを出してくれます。
ですが、濁りの原因ともなるので、
澄んだダシを引きたいときには、血合いを取り除いたものを使います。
もちろん、ご家庭でのお料理には血合い入りで充分ですし、
お好みのおだしでO.K.ですよ~^^
鍋に
水 1リットル
昆布 10g
を入れて中火に掛けます。

湯気が立ってきたら、プツプツ沸騰してくるまえに
早めに昆布を取り出します。

取り出した昆布は、2番だしが取れますよ。
沸騰したら
コップ1杯くらいの差し水をして、

削り25~30g を入れます。

ひと煮立ちしたら火を止め、

そのまま1~2分置きます。
削りが沈むまで待つのが理想のようですが、
なかなか沈まないので、1~2分置いたらこします。

ここに、
日本酒 大さじ 1/2

塩 小さじ 1/2

を入れて、味加減をみます。
1リットルよりもやや多目のダシの量ですから
と~っても薄味ですが、
この控えめな味がいいんですよ~^^
松茸 1本
乾いた布巾で汚れを拭き取ったら

石づきを落として

食べやすい大きさに切って
鍋に入れて、

沸騰させないように2分くらい中火に掛けます。

一つまみの塩を入れてゆでて

薄皮をむいた、銀杏。

輪ゴムでまとめて、

ひとつまみの塩を入れたお湯でさっとゆでた
三つ葉を

お椀に入れておいて、

注ぎます。

ちょっと薄かったかしら~ と感じるひとくち目ですが、
二度目に口に運んだとき、
美味しい~!と、感動できます。
ダシの奥深さを堪能できる一品です^^
2009年11月10日
ワタリガニのお味噌汁
今朝のお味噌汁は、ワタリガニ。

伊東の知人から、ワタリガニをいただきました。

200gの大きなワタリガニです。
きれいに洗ったら、
お腹から切ります。

頭?目を向こう側にして、真ん中に出刃包丁を入れます。
押し付けるように切ります。

向きを変えて、頭を手前にして

ぎゅっと包丁を入れて、半分になりました。

さらに半分ずつにして

4切れになりました。
身も、そこそこあるようです^^
もっと小分けに切ってもいいですし、
小さなワタリガニで、食べる身が少ないようでしたら
出刃包丁の背でたたいてつぶすと、
見た目は良くありませんが、よりダシが出ます。
ワタリガニからダシが出るので、
水800ccを火に掛けました。
(実は、きも~ちカツオダシも入っています^^)
沸騰したところにワタリガニを入れて

ワタリガニの色が変わってきたら、

火を止めて味噌を溶いて、出来上がりです。

お椀からはみ出している、ワタリガニ♪
カニ味噌も浮いています♪♪

朝から幸せな一杯です^^

伊東の知人から、ワタリガニをいただきました。

200gの大きなワタリガニです。
きれいに洗ったら、
お腹から切ります。

頭?目を向こう側にして、真ん中に出刃包丁を入れます。
押し付けるように切ります。

向きを変えて、頭を手前にして

ぎゅっと包丁を入れて、半分になりました。

さらに半分ずつにして

4切れになりました。
身も、そこそこあるようです^^
もっと小分けに切ってもいいですし、
小さなワタリガニで、食べる身が少ないようでしたら
出刃包丁の背でたたいてつぶすと、
見た目は良くありませんが、よりダシが出ます。
ワタリガニからダシが出るので、
水800ccを火に掛けました。
(実は、きも~ちカツオダシも入っています^^)
沸騰したところにワタリガニを入れて

ワタリガニの色が変わってきたら、

火を止めて味噌を溶いて、出来上がりです。

お椀からはみ出している、ワタリガニ♪
カニ味噌も浮いています♪♪

朝から幸せな一杯です^^
2009年07月12日
かき玉汁
梅雨の蒸し暑い日が続いていますが、
今日は、温かい かき玉汁です^^

今月になってから、学区の中学2年生4クラスの家庭科の授業で
おだしの話をさせていただく機会がありました。
ダシの異なる4種類のお味噌汁の飲み比べから始まって、
日本のダシ文化の話から、いろいろなおだしの種類の話など・・・
2時間続き授業の後半は、実際におだしを取って、かき玉汁を作りました。
生徒たちは、
あご(トビウオ)ダシ ・ 昆布かつおダシ の2グループに分かれましたが、
今日は、定番の 昆布・かつおダシ の、かき玉汁です。
2人分 400ccの水に 昆布を入れておきます。

昆布は4cm角くらい。
できれば1~2時間つけ置くといいです。
漬け置いた昆布を、中火~弱火にかけます。

少ない分量のダシを取るので、一気に沸騰しないように火は弱めにします。
ぷつぷつ沸騰してきたら、

昆布を取り出し、
昆布はそのまま食べちゃいましょう。
かつお削り 12~3gを入れます。

沸騰したら、30秒ほど煮立て

火を止めます。
2番ダシを取るときに、煮立ったらすぐに火を止めますが
一回しかダシを引かないので、少し煮立てます。
網ですくって、こします。

もう一度 中火にかけたら、
塩 小さじ1 /2

醤油 小さじ1/2 を入れて

ひと煮立ちさせて、調味料とダシをなじませます。
ここで、水溶き片栗粉を加えると こっくり仕上がります。
溶きたまご 1/2個分を

菜ばしに沿わせるように、円を描きながら流して
出来上がりです。

アゴダシで作ったかき玉汁と、昆布・かつおダシで作ったかき玉汁を飲み比べて、
ダシが違うと こんなにも味が変わるのだと、舌で感じてもらえたようです。
おだしを取り終わった後のカツオ削りで作ったふりかけも、大好評~!
同じくダシを取った後のトビウオも綺麗に食べてくれた生徒さんもいて、
”いのち”を感謝していただいてもらうことができて、
嬉しい時間が持てました。
そして、もうひとつ楽しませていただいたのが、給食の時間。
1日目は、カレーうどん。

コーンコロッケと、もやしのサラダ。
翌週は、三島西麓じゃがいもの ポテトグラタン。

トマトスープと、カルピスゼリーのデザートです^^
何〇年ぶりかの給食で、ワクワクしたのですが
調理準備室でひとり食べる給食は、やっぱりちょっと寂しかったかしら?^^
学校で作ったかき玉汁は、玉子だけの具でしたが、

ワカメやネギを加えれば、彩りもきれいですね^^
今日は、温かい かき玉汁です^^

今月になってから、学区の中学2年生4クラスの家庭科の授業で
おだしの話をさせていただく機会がありました。
ダシの異なる4種類のお味噌汁の飲み比べから始まって、
日本のダシ文化の話から、いろいろなおだしの種類の話など・・・
2時間続き授業の後半は、実際におだしを取って、かき玉汁を作りました。
生徒たちは、
あご(トビウオ)ダシ ・ 昆布かつおダシ の2グループに分かれましたが、
今日は、定番の 昆布・かつおダシ の、かき玉汁です。
2人分 400ccの水に 昆布を入れておきます。

昆布は4cm角くらい。
できれば1~2時間つけ置くといいです。
漬け置いた昆布を、中火~弱火にかけます。

少ない分量のダシを取るので、一気に沸騰しないように火は弱めにします。
ぷつぷつ沸騰してきたら、

昆布を取り出し、
昆布はそのまま食べちゃいましょう。
かつお削り 12~3gを入れます。

沸騰したら、30秒ほど煮立て

火を止めます。
2番ダシを取るときに、煮立ったらすぐに火を止めますが
一回しかダシを引かないので、少し煮立てます。
網ですくって、こします。

もう一度 中火にかけたら、
塩 小さじ1 /2

醤油 小さじ1/2 を入れて

ひと煮立ちさせて、調味料とダシをなじませます。
ここで、水溶き片栗粉を加えると こっくり仕上がります。
溶きたまご 1/2個分を

菜ばしに沿わせるように、円を描きながら流して
出来上がりです。

アゴダシで作ったかき玉汁と、昆布・かつおダシで作ったかき玉汁を飲み比べて、
ダシが違うと こんなにも味が変わるのだと、舌で感じてもらえたようです。
おだしを取り終わった後のカツオ削りで作ったふりかけも、大好評~!
同じくダシを取った後のトビウオも綺麗に食べてくれた生徒さんもいて、
”いのち”を感謝していただいてもらうことができて、
嬉しい時間が持てました。
そして、もうひとつ楽しませていただいたのが、給食の時間。
1日目は、カレーうどん。

コーンコロッケと、もやしのサラダ。
翌週は、三島西麓じゃがいもの ポテトグラタン。

トマトスープと、カルピスゼリーのデザートです^^
何〇年ぶりかの給食で、ワクワクしたのですが
調理準備室でひとり食べる給食は、やっぱりちょっと寂しかったかしら?^^
学校で作ったかき玉汁は、玉子だけの具でしたが、

ワカメやネギを加えれば、彩りもきれいですね^^